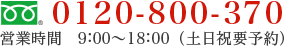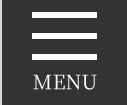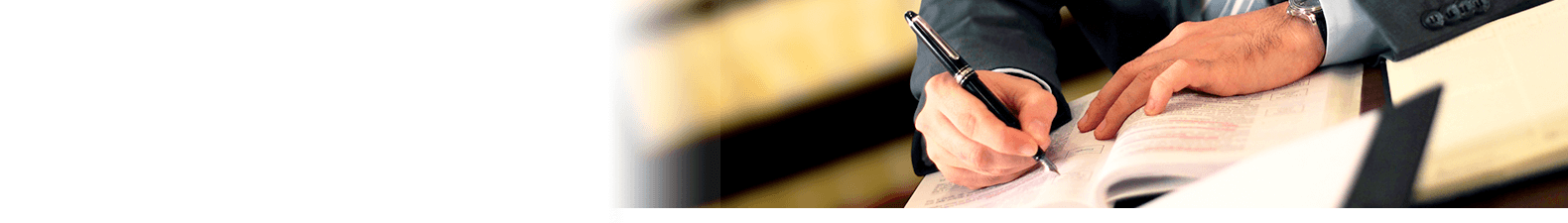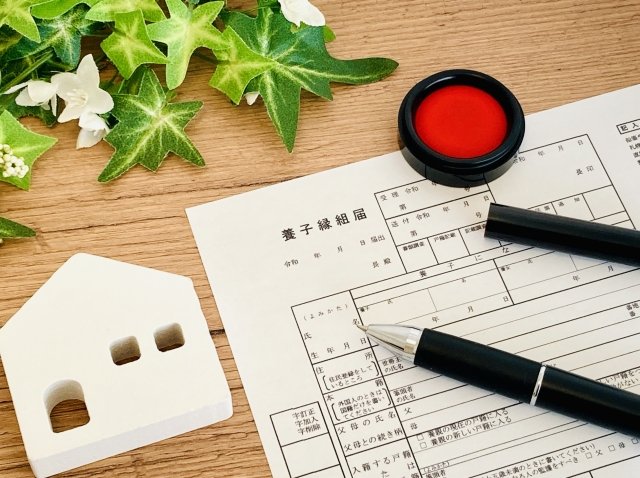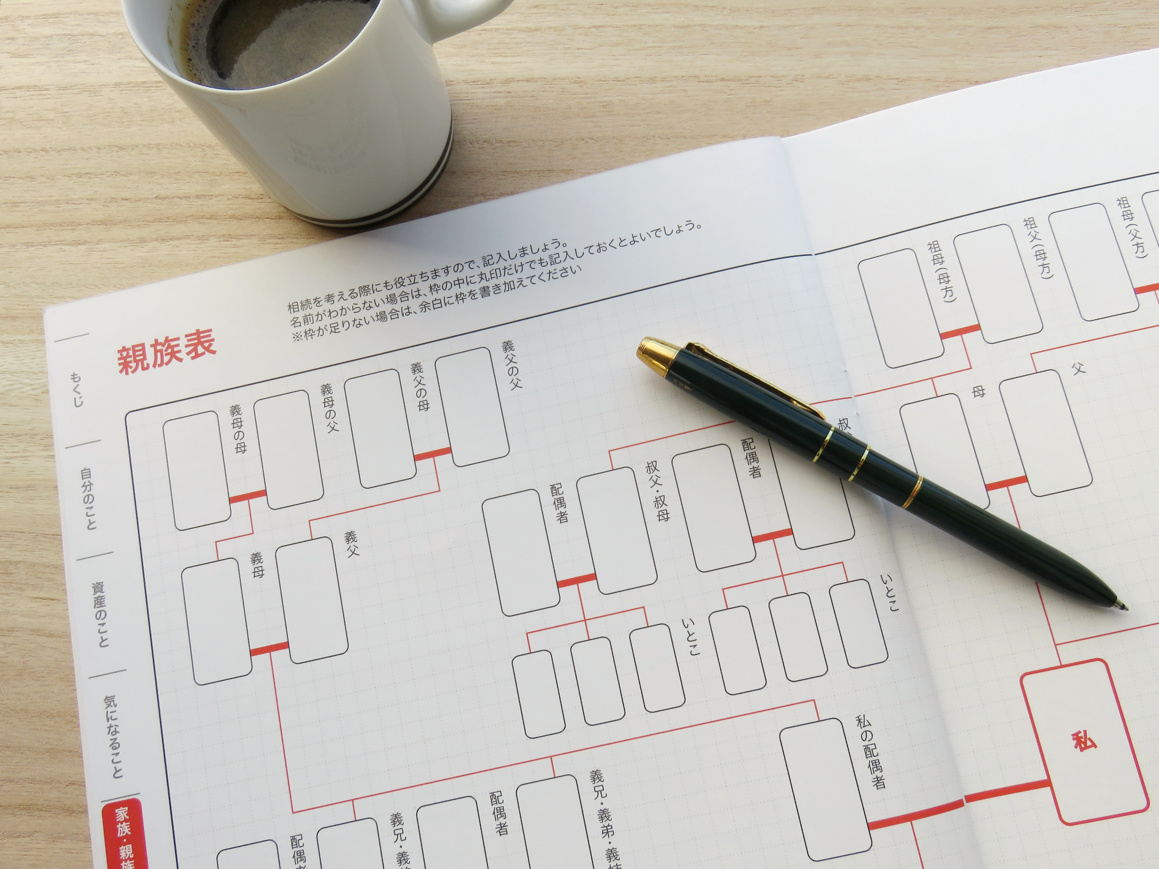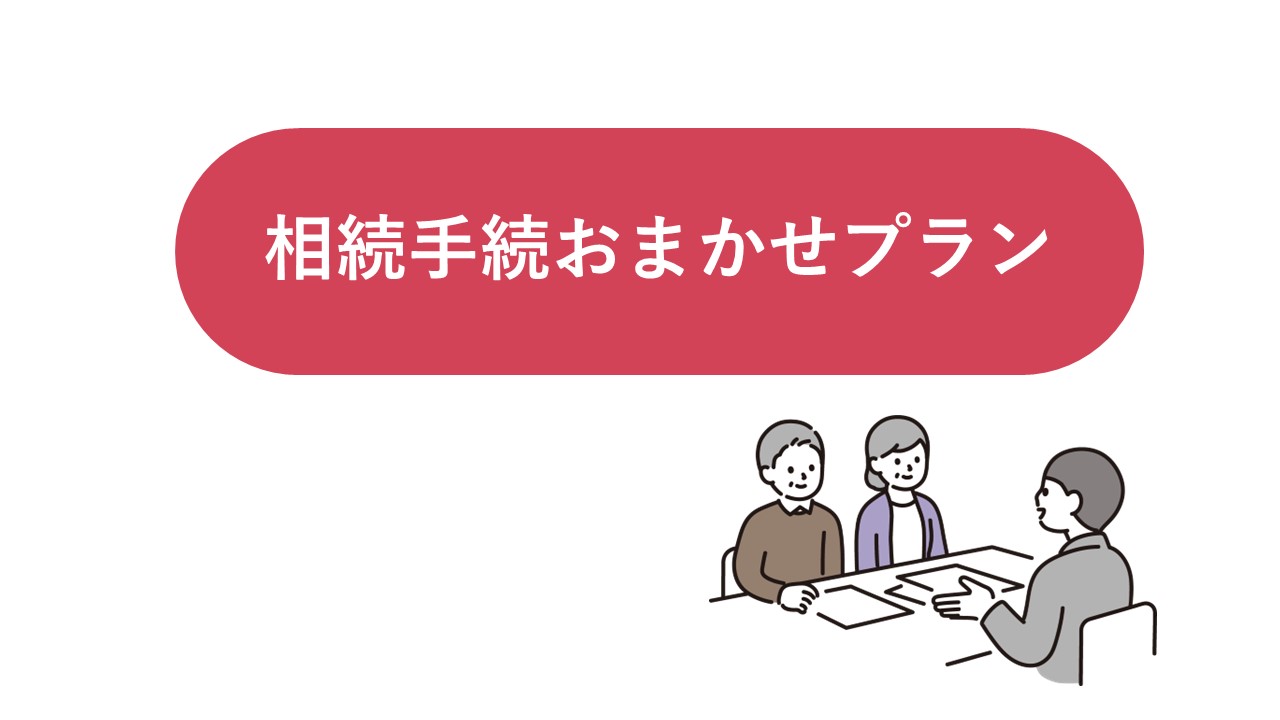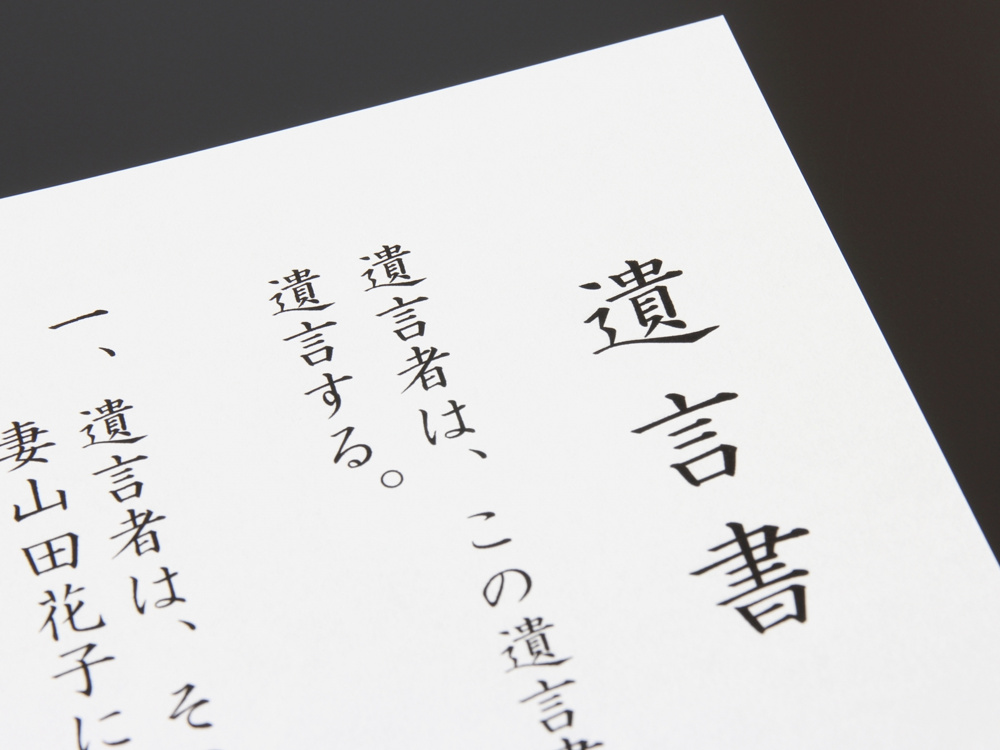司法書士法人リーガル・フェイスの北でございます。
今回は、養子縁組と相続対策についてお伝えさせていただきます。
相続対策を考える際、税金の負担や財産分配の公平性は避けて通れない課題です。
その中で、養子縁組は、縁組という形でご一家の絆を深めながら相続税を軽減するということも可能です。
そして、特定の人に財産を確実に承継できる強力な手段として注目されています。
しかし、その効果を最大限に活用するためには、法律や税制の基礎知識を理解し、早い段階から計画的に進めることが重要です。
本コラムでは、養子縁組を活用した相続対策の基本から縁組のメリット、注意点まで、わかりやすく解説します。
【目次】
1.養子縁組の種類
養子縁組には以下の2種類があります。
普通養子縁組
実親との親子関係を維持しつつ、養親との親子関係を新たに結ぶもの。
養子は実親と養親の両方の相続権を持ちます。
普通養子縁組をするための主な要件は、以下のとおりです。
●養親は20歳以上でなければならない。
●養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要。
※養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をする。
●養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要。
●養子縁組は、市区町村の役所への届出によって効力を生じる。
【未成年者(18歳未満)を養子とする場合は、下記要件も必要】
① 配偶者がいる場合、配偶者とともに養子縁組をすること(夫婦共同養子縁組)
② 家庭裁判所の許可(審判)を受けること
特別養子縁組
実親との親子関係は終了し、養親との親子関係のみを結ぶもの。
原則として養子は15歳未満である必要があり、家庭裁判所審判手続きが必要です。
特別養子縁組をするための主な要件は、以下のとおりです。
養親について
特別養子縁組については、養親は配偶者のいる者でなければならず、また、夫婦共同縁組をする必要があるとされています。
また、年齢については、養親となる夫婦の一方が25歳以上(もう一方は20歳以上)でなければならないとされています。
養子について
養子となる方の年齢は、原則として15歳未満である必要があります。
実親の同意
特別養子縁組については、養子となる子供の実父母の同意が必要であるとされています。
ただし、実父母がその意思を表示できない場合、又は、実父母の虐待、悪意の遺棄その他養子となる子供の利益を著しく害する事由がある場合には、同意は不要とされています。
6ヵ月間の監護
特別養子縁組の成立のためには、養親となる方が養子となる子供をあらかじめ6ヵ月以上監護することが必要であり、家庭裁判所は、その監護の状況等も考慮して、特別養子縁組の成立を決めることになります。
【ポイント】
養子となる子供の利益のために特に必要があること
家庭裁判所の許可(審判)を受けること
2.養子縁組を活用した相続対策のメリット
① 相続税の節税効果
養子を迎えることで法定相続人の数が増え、相続税の基礎控除額が増加します。
(基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数)
ただし、下記注意点がありますのでご確認ください。
※税法上の養子の人数計算は専門知識が欠かせないため、個別具体的な事例については税理士に必ず確認をしてください。
(1)亡くなった人に実子がいた場合
法定相続人に含める養子の数は、1人までです。
(2)亡くなった人に実子がいなかった場合
法定相続人に含める養子の数は、2人までです。
ただし、上記の計算が相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その計算は否認される可能性もあります。
② 生命保険金や死亡退職金の非課税枠も増加
(非課税枠:500万円×相続人の数)
③ 財産の分配先を増やせる
養子縁組を通じて、法定相続人以外の人(例:孫や子の配偶者)に財産を確実に渡すことが可能です。
さらに、親族以外の人との養子縁組も可能ですので、養子が家業や事業を引き継ぐ場合に利用される方もいらっしゃいます。
3.養子縁組のデメリットと注意点
① 孫養子の場合の税負担増加
孫を養子にした場合、相続税が2割加算される規定があります。
② 養子縁組の解消が難しい
養子縁組を解消するには、養親子間の合意に基づいて市区町村に協議離縁の届出をするか、又は、離縁の訴えを提起する必要があります。
③ 他の相続人の相続分が減ることによる家族関係への影響
養子縁組によって法定相続人が増えるため、他の家族が不満を抱く可能性があります。
特に養子が義務を果たさない場合や親族間で意思疎通が不足している場合、関係性が悪化するリスクがあります。
④ 相続税が増えるケースがある
非常にまれなケースかとは思いますが、相続税が増える事例もあります。
例えば、養子縁組前の段階で、被相続人となる人には親も子もおらず姪甥一人ずつが相続人だとします。法律上は相続人は2人です。
しかしながら、この場合で、被相続人となる人と姪にあたる方が養子縁組をした場合は、養子が第一順位の相続人となり、法定相続人は養子一人のみとなるというケースです。
4.養子縁組を活用する際のポイント
① 家族間の合意形成
養子縁組を行う前に、家族全員で十分な話し合いを行い、合意を得ることが重要です。
特に養子縁組によって誰がどのくらいの財産を受け取るのかを明確にし、不公平感が生じないように配慮する必要があります。
② 専門家への相談
税理士や弁護士に相談し、節税効果や法的リスクを十分に検討した上で進めることをお勧めします。
③ 目的を明確にする
節税を目的にした場合、税法上の制限やリスクがあるため、他の方法(生前贈与や遺言書の活用)と併用することを検討するのも一つの手です。
5.養子縁組を活用した具体的なケース
ケース1: 基礎控除額を増やして相続税を節税
あるご家族では、子供が1人(実子)いる被相続人(親)が養子を1人迎えました。
この養子縁組によって法定相続人の数が「2人」になり、相続税の基礎控除額が以下のように増加しました。
基礎控除額の計算式:3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
養子を迎える前:3000万円 + 600万円 × 1人 = 3600万円
養子を迎えた後:3000万円 + 600万円 × 2人 = 4200万円
これにより、3600万円以上の遺産があったとしても、課税される額が大幅に減少しました。
ケース2: 孫を養子にして財産を次世代に渡す
高齢の祖父が孫を養子にしました。
これにより、孫は祖父の法定相続人となり、祖父の財産の一部を直接相続できるようになりました。
また、孫を養子にすることで財産が次世代に早く渡るため、相続税を2世代に分散させる効果も得られました。
この場合は注意点もございます。孫が養子になったことで相続税の「2割加算」が適用され、孫の税負担が増える結果にもなりました。
ケース3: 特定の人物に財産を確実に渡す
子供がいない夫婦で、夫が養子縁組を通じて妻の甥を養子にしました。
この養子縁組によって、甥は法定相続人となり、夫の死後に遺産を受け取れることになりました。
養子縁組をしない場合、亡くなった時点の相続関係にもよりますが、甥は相続人としての資格を持たず、夫の意思を実現できない可能性がありました。
6.養子縁組の手続き方法について
養子縁組の手続き方法について、以下のステップごとに説明します。
普通養子縁組と特別養子縁組で若干手続きが異なりますが、ここでは一般的な普通養子縁組の流れをご説明いたします。
① 養子縁組の準備
●目的を明確にする
養子縁組をする理由を整理します。(例:相続対策、家業承継、家族としての絆の強化など)。
●関係者への説明
実子や他の家族に事前に養子縁組の意図を説明し、可能な限り合意を得ておくことが重要です。
●必要書類を確認する
養子縁組を進めるために必要な書類を事前に確認します。
② 必要書類の収集
養子縁組に必要な書類は以下の通りです。ケースによって追加書類が必要になる場合があります。
◆養親と養子の戸籍謄本 ※本籍地の役場に届出る場合は不要
◆未成年者の場合養子縁組許可審判書
◆本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)。
③ 養子縁組届を作成
④ 届出の提出
◆役所で手続きが完了すると、戸籍に養子縁組の記載が反映される。
⑤ 養子縁組が成立
◆養子縁組が戸籍に反映されれば、法的に養親と養子の関係が成立する。
この時点で、養子は養親の法定相続人となります。
7.まとめ
養子縁組の手続き自体は比較的シンプルですが、相続や家族関係に与える影響は大きいため、慎重な準備が求められます。
養子縁組を検討する際は、まず家族全員で十分な話し合いを行い、合意を形成することが重要です。
養子縁組は一度成立すると元に戻すのが難しいため、慎重な判断が求められます。
司法書士、税理士、弁護士などの専門家と連携し、適切な計画を立てましょう。
特に税務の判断は税理士に個別に確認することが必要でしょう。
リーガル・フェイスではお客様にお悩みにあった税理士のご紹介もしております。
生前対策は、養子縁組以外にも遺言、任意後見等もございます。
今何が必要か総合的な判断が求められますので、生前対策でお悩みでしたらぜひリーガル・フェイスまでお問い合わせください。

千葉県勝浦市生まれ、東京育ち。平成17年に司法書士試験合格。不動産会社・金融関係の企業勤務を経て、相続関連の業務に携わりたいという想いから司法書士法人リーガル・フェイスに入社。主な資格は司法書士、宅地建物取引主任者、貸金業務取扱主任者。趣味は自宅で行うヨガ。好きな食べ物はリーフパイ、お好み焼き、酢めし、磯辺焼きなど。