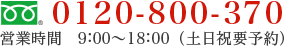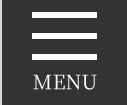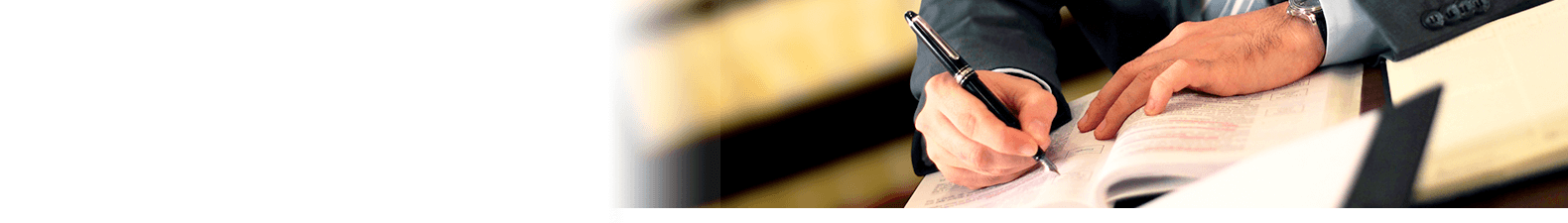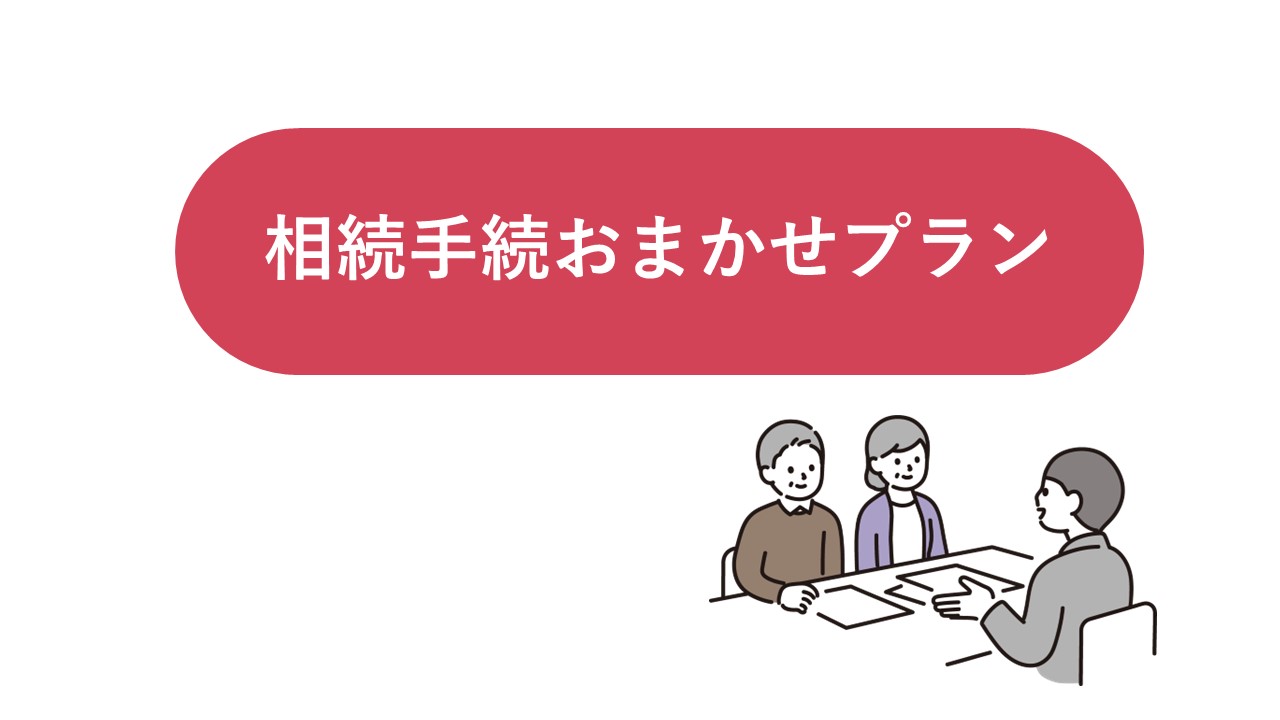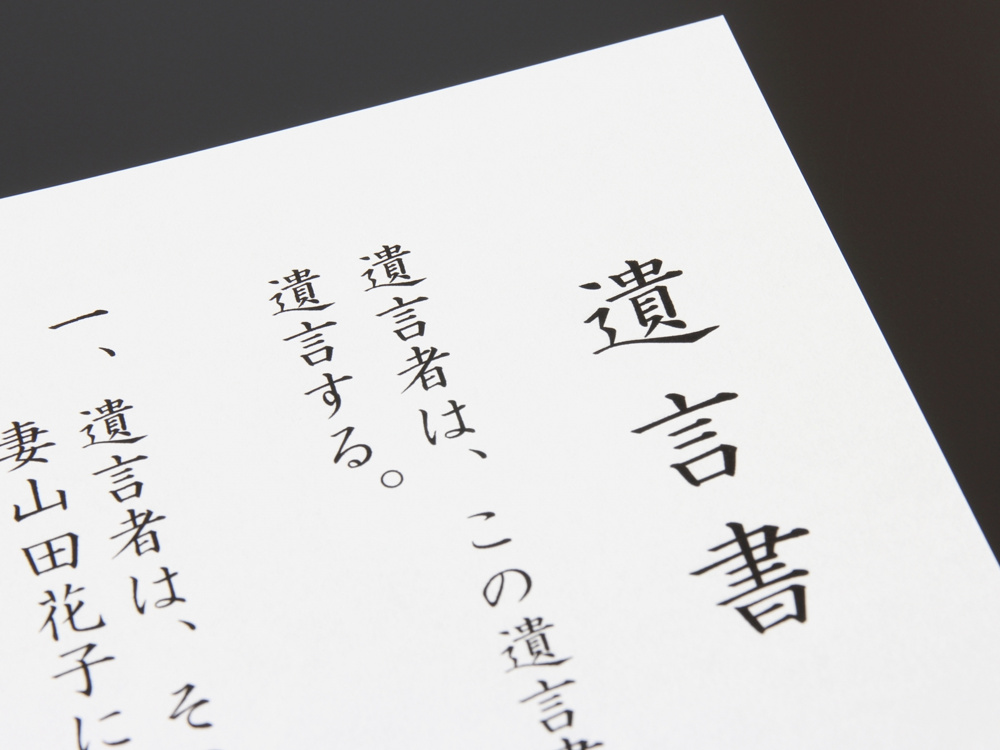相続した不動産に農地が含まれる場合、通常の不動産の相続手続きに加え、農地法などの法律による規制により、農地特有の手続きが必要となります。
農地法は、食料の安定供給の確保に資することを目的として、国内の農業生産の基盤である農地の利用関係を規制する法律です。
相続した不動産に農地が含まれていた場合に、どのような対応が必要か、以下で概略を説明します。
【目次】
1.農地を相続した際に必要となる手続き
農地を相続した際には、法務局での相続登記と農業委員会への届出という二つの手続きが必要となります。
■相続の登記について
まず、相続によって農地を取得したときは、相続の登記が必要です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を相続した場合、その相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象です(令和9年3月31日までに相続登記が必要です)。
相続登記の申請の際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍等を、市区町村役場で取得する必要があります。
また、相続人が複数いる場合には、遺言書がない限り、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、だれがどのように遺産を受け継ぐかを話し合いで決める必要があります。
このように、書類を集めたり話し合いをしたりと、時間のかかる手続きのため、相続税の申告が必要な場合や、以下で説明するように農業委員会への届出の期限を考慮して、なるべく早めに動き出すことをおすすめします。
■相続の届出について
次に、相続によって農地を取得したときは、その農地の所在する市町村の農業委員会へ届出をする必要があります(農地法3条の3)。
この届出は、相続発生日からおおむね10か月以内にする必要があります。
届出の際には、届出書と併せて、全部事項証明書や遺産分割協議書など、農地の権利を取得したことがわかる書類が必要です。
なお、この届出は、上記で説明した相続登記とは別に必要な手続きですので、忘れずに行う必要があります。
届出を行わなかった場合、10万円以下の過料に科される可能性があります。
また、相続したものの、地元を離れてていて管理ができない場合には、農業委員会が管理の相談や、借り手を探す手伝いをしているようです。
届出の際に管轄の農業委員会へ相談するとよいでしょう。
2.相続した農地の活用について

次に、相続した農地をどのように活用するかを、相続人が農業を行う場合と行わない場合に分けて説明します。
■農業を行う場合
相続した農地で農業を行う場合には、特に手続きは必要ありません。
■農業を行わない場合
相続人が農業を行わない場合は、①農地を農地のまま売却、貸付する方法と、②農地を転用する方法が考えられます。
①農地を農地のまま売却、貸付する
農地を農地のまま売却、貸付する場合は、原則として、当事者がその農地の所在する市町村の農業委員会へ申請し、許可を受ける必要があります(農地法3条)。
この許可を受けていない売買等は無効となります。
また、売却や貸付の相手方は、「機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること」などの、一定の要件を満たした個人や法人に限られます。
なお、自身で借り手を探したり契約交渉したりせず、農地中間管理機構(農地バンク)に貸付けるという方法もあります。
②農地を転用する
農地の転用とは、農地を宅地や駐車場などの農地以外のものにすることです。
自身の所有する農地であっても自由に転用はできず、原則として、都道府県知事等の許可が必要です。
自分で別の用途に使う場合は農地法4条の許可を、他の人や会社に売却して転用するときは農地法5条の許可を受ける必要があります。
また、農地が市街化区域内である場合は、都道府県知事の許可に代わり、農業委員会への届出で足ります。
3.おわりに
以上、相続した不動産に農地が含まれていた場合の対応について、概略を説明しました。
リーガル・フェイスでは、相続全般のサポートをさせて頂いておりますので、お困りごとがありましたらご相談ください。
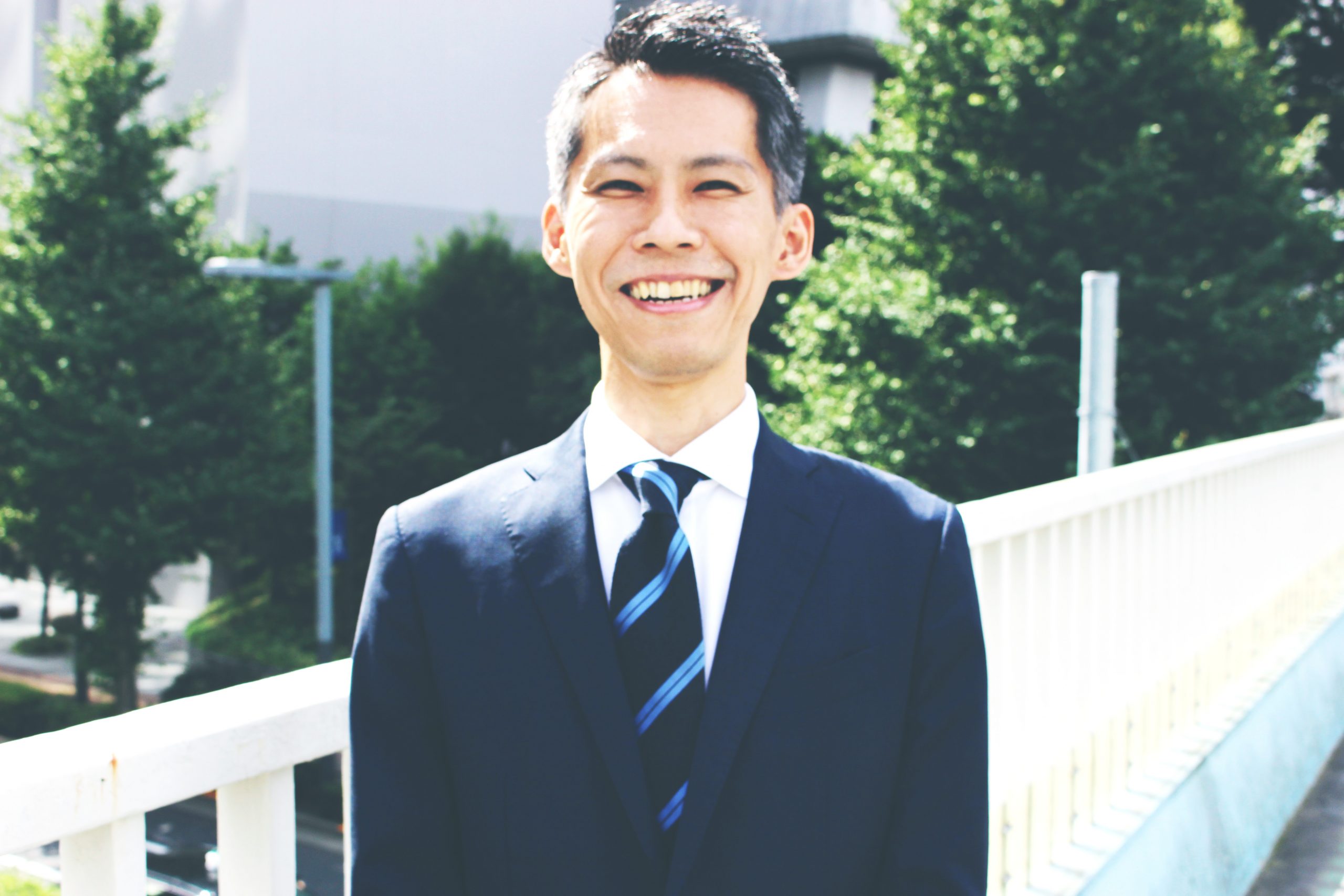
埼玉県熊谷市出身。司法書士の"争いが起こらないようにする仕事である"という業務内容に魅力を感じ、勉強を開始する。アルバイトをしながら資格勉強に励み、数年後に司法書士資格を取得。都内司法書士法人、会計事務所での経験を経て2022年リーガル・フェイスへ入所。趣味は美味しいものを食べながらビールを飲むこと。高校時代は野球部、大学時代は混声合唱サークルに所属。好きな食べ物は唐揚げ、ハンバーグ、カレーなど。