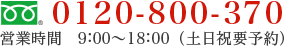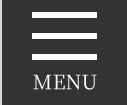1. 相談の背景
公正証書遺言の作成のご依頼
数年前に大病を患ったため、長年連れ添った奥様の生活を考えて奥様に全財産を残したい。
万一のことを考えて遺言書を公正証書で作成しておきたいと希望されてのご依頼でした。
2. 相談に対する弊所の対応
遺言書を作成したいとお考えになる動機としては次のようなことが考えられます。
①自分が亡くなった後、相続人間での遺産分割で争いがないようにしたい。
たとえば、子供たちの仲が悪く財産の取り分で争うことが予想される場合です。
仲が悪くなくても人とはお金が絡むと争いとなる可能性があるものです。
このような争いを避けるために、遺言書を作成しておき財産の取り分を決めておくことができます。
②法定相続人のうちの特定の人に財産を残したい、例えば自分に妻がおり、自分が亡くなったあと妻とその他の相続人間での遺産分割で苦労をかけたくない。
この場合に妻に全財産を相続させるという遺言書を作成しておくことにより、妻が全て相続することができるようになります。
③法定相続人以外のお世話になった人や慈善団体などに財産を渡したい。
このような場合、生前に口頭で「私が死んだら●●に財産を渡してほしい」と言っておいても法律上の効力はありません。
これを実現するには遺言書を作成しておかなければなりません。
本件では②の動機に近いものでした。
遺言書を作成するにあたり、まずは法定相続人を調べておくことが必要となります。
そこで弊所にて戸籍謄本を収集しました。法定相続人は、依頼者様の奥様、ご子息2名であることがわかりました。
今回の懸念点としては、「奥様に全財産を相続させる」という遺言書を残したとしても、ご子息たちには遺留分があることです。
遺留分とは遺言によっても奪われない相続財産に対する一定の割合を法定相続人に保証するものです。
奥様がご子息たちから遺留分の主張をされた場合、その割合に相当する金銭を支払わなければなりません。
しかし、遺留分に抵触する遺言も有効な遺言ですし、遺留分の主張が必ずされるわけでもありません。
遺留分の主張がされなければ遺言書に書いたことがそのまま叶います。
この点を依頼人にご説明したところ納得され、遺言書の作成を進めたいとのことでした。
次に、依頼人ご自身において遺言書に特に明記しておきたい財産をご教示いただき、弊所にて当初の遺言書の文案を作成しました。
次に弊所作成の遺言書文案と戸籍謄本や遺言書に明記する財産の資料などをもとに公証人と打ち合わせを行い、遺言書の文案を完成させていきました。
その文案をご依頼人に提示して了解をいただいたうえで、公証役場に公正証書遺言作成をする日時の予約を取りました。
そして・・・・・その日を待ちます・・・・・・
3. 結果
遺言書の完成
予約した日時に、依頼人が遺言者本人として、弊所から2名が遺言書作成に立ち会う証人として、公証役場に集まりました。
そして公証人が遺言書を読み上げ、依頼者ご本人、証人2人が内容に間違いない旨を確認し、署名捺印して遺言公正証書が完成しました。
依頼人は「これで妻に財産を残せる」とご安心しておりました。
そして喜んでご帰宅されていきました。