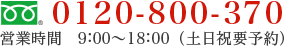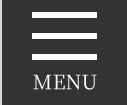1. 相談の背景
認知症の父と自分が亡き母の相続人になったが・・・
1年前にお母様が逝去されたAさんが、無料相談会にいらっしゃいました。
ご家族はお父様・子ども(3人兄弟のAさん・Bさん・Cさん)の4名です。
また、数年前から、Aさんが認知症のお父様の成年後見人として選任されているとのお話しでした。
Aさんは、お母様名義の不動産や預貯金について一度ご自身で相続手続きを試みようとされましたが、どのように進めたらいいか判然とせず困ってしまい、そのような中でリーガルフェイスのHPをご覧になり、無料相談会の実施をお知りになったとの事でした。
2. 相談に対する弊所の対応
利益相反と特別代理人
通常の相続手続きの場合、法定相続人全員が話し合い(遺産分割協議)を行ない、誰がどの遺産をどれくらい相続するかを決定します。
相続人が認知症などで話し合いに加われない場合は、本人の代わりに成年後見人が代理人として分割協議を行います。
今回のケースにあてはめると、成年後見人のAさんが認知症のお父様の代理人として遺産分割協議を行えば問題無いように思われがちですが、実はそうではありません。
ここで大事になってくるのが「利益相反行為」という考え方です。
利益相反行為とは、自分の利益と他人の利益が対立する(自分の利益が他人の不利益となる)行為の事をいいます。
認知症の親と成年後見人の子が同じ相続人としての立ち位置である場合、子が親の代理人として、親に財産を渡さないなどの子自身の利益を追及してしまう行為(=利益相反行為)が可能となってしまいます。
このような事態を避けるため、成年後見人とは別の「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらい、その「特別代理人」が認知症の親の代理人として遺産分割協議に参加する、という手続きを踏む必要があります。
今回のケースにおいては、お父様とAさんはどちらも亡きお母様の相続人ですので、成年後見人であるAさんはお父様の代理人として遺産分割協議を行うことができません。
したがって、上記の通り家庭裁判所で特別代理人選任の手続きをリーガルフェイスでお手伝いさせていただき、新しく選任されたお父様の特別代理人・Aさん・Bさん・Cさん間で遺産分割協議を行いました。
3. 結果
無事に遺産分割協議と相続手続きが完了
上記の遺産分割協議書や、家庭裁判所から発行された特別代理人の選任審判書などの必要書類を整え、無事に不動産や預貯金などの相続手続きを適正に行うことができました。
特別代理人の選任には1カ月半ほど時間を要しましたが、Aさんのご協力もありスムーズに手続きが進みました。