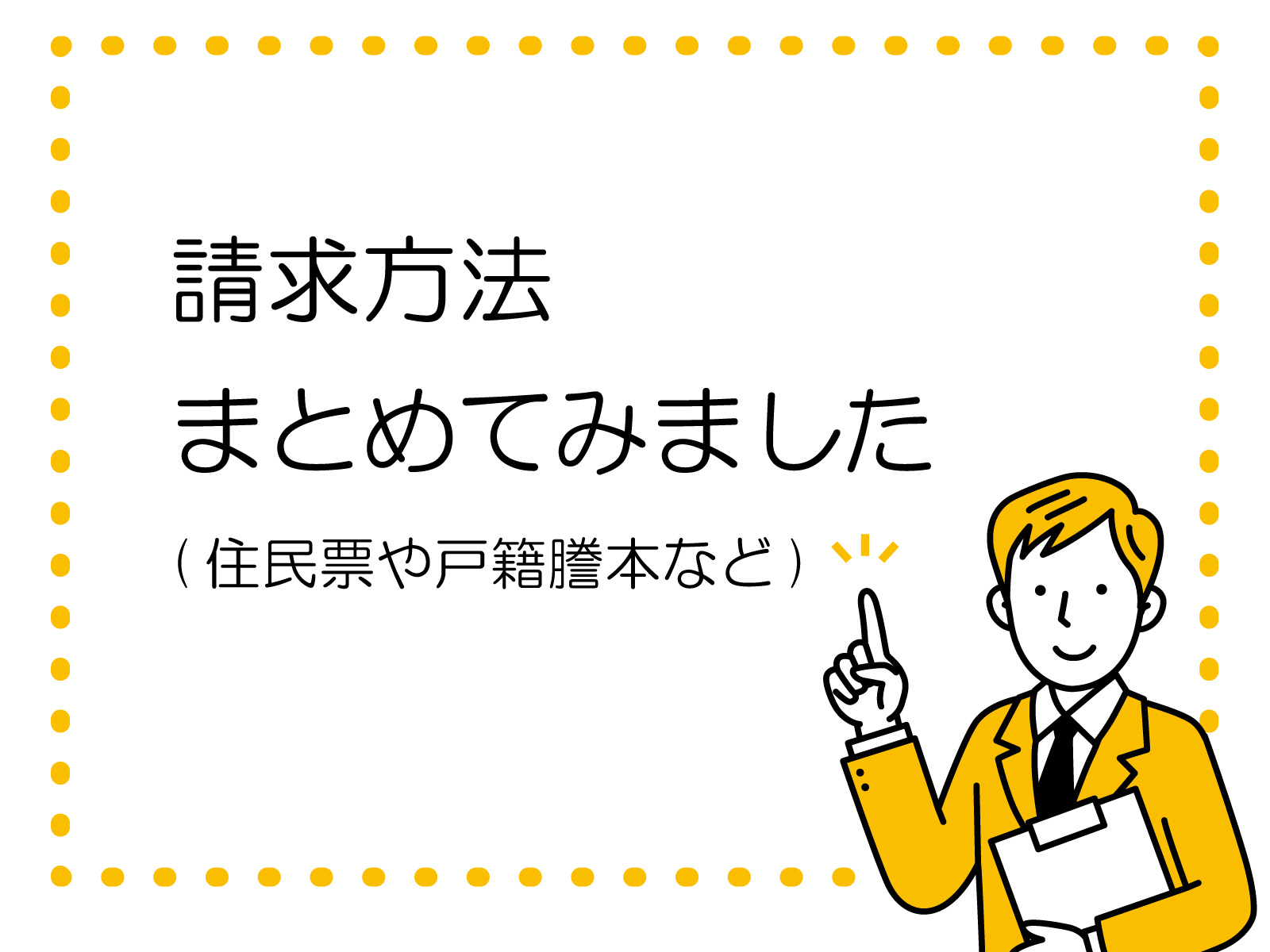
こんにちは、錦糸町支店の吉田です。
今更ですが、私たち事務所(と言うよりも業界全体?)の主な業務は登記申請業務です。
登記申請はざっくり言えば依頼人の代わりに法務局に書類を提出し、審査を受け、登記簿を書き換えてもらう……という一連の流れのお仕事。
そしてこの時に使用する書類をいかにスムーズに、正確に用意できるかが腕の見せ所でもあります!
さて、そんなとても大切な書類ですが、大きく分けて『私文書』(個人間の契約書、自筆証書遺言など)と『公文書』(住民票、登記簿謄本など)の二種類があります。
前者は主に依頼人や関係者の方から直接お預かりしたり、書類によっては私たちで作成をして準備をします。
それに対し後者は国や地方自治体が作成した公的な書類ですので、書類の種類に応じて管轄の公的機関へ請求し交付を受ける必要があります。
そしてこの請求を正しく行うためにはしっかりと請求先や必要書類などを把握しておくのが大切なのです。
今回はそんな公文書の中から、主に登記で多く使用されるものに絞って解説していきたいと思います。
Ⅰ.市区町村の役所(役場)で交付を受ける事ができるもの
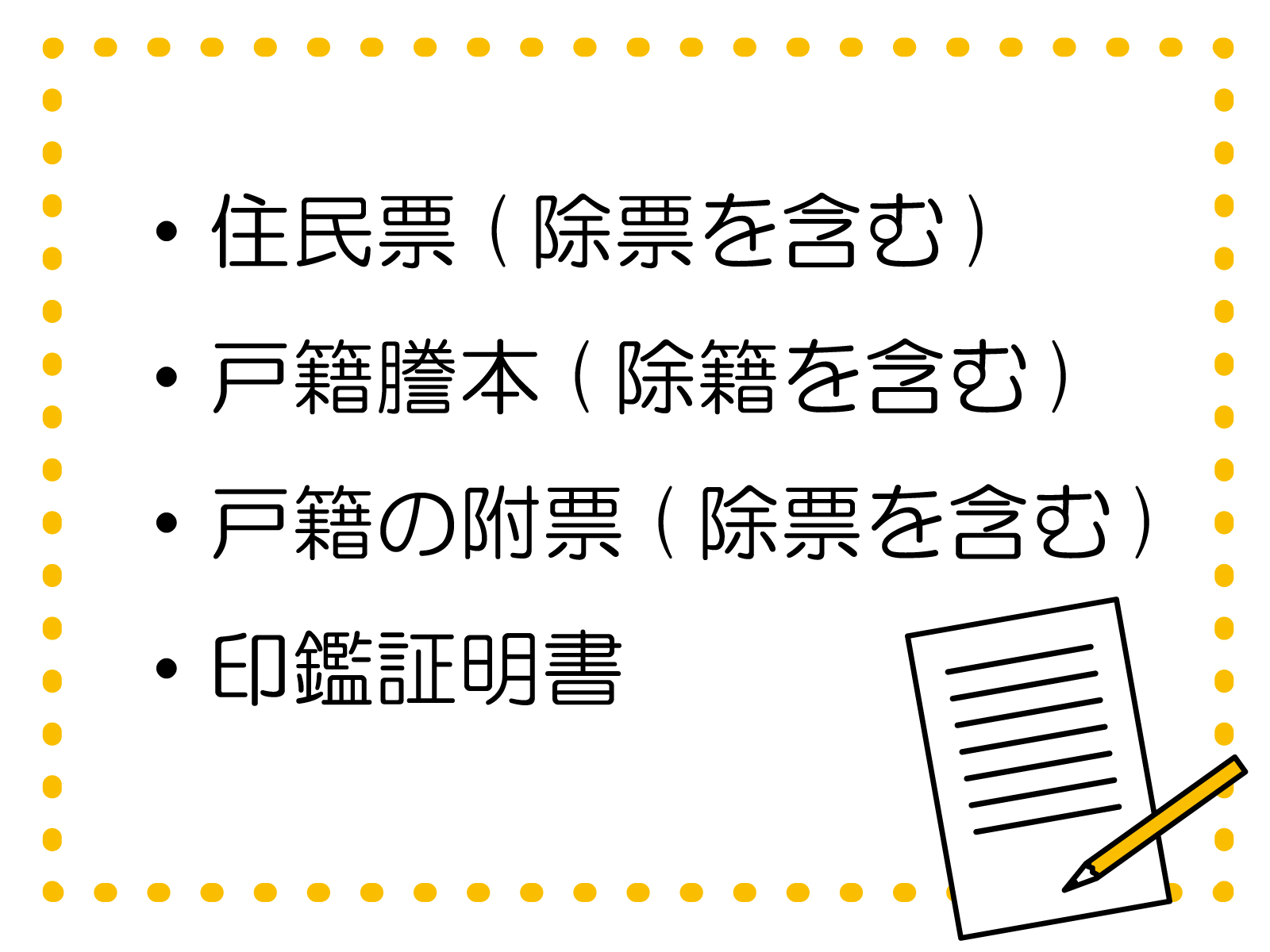
※除票や除籍とは、既に現行の書類から削除された情報が記載されたものの事を言います(引っ越しをして住民票を異動した場合や結婚によって親の戸籍を離脱した場合など)。
まずは、登記以外の場面でも必要になる事が多いと思われる書類たちです。
これらはその住所地(戸籍謄本、戸籍の附票は本籍地)を管轄する市区町村の役所(役場)の戸籍住民課で交付を受ける事ができます。
(利用者が多い部署なためか、たいていの役所(役場)で建物に入ってすぐにこの窓口があるイメージです)
交付方法について一つずつ見ていきましょう。
住民票
【交付を受ける事ができる人】
① 住民票に記載されている人
② ①から委任を受けた代理人
【管轄役所以外での交付】
コンビニ→〇 他管轄の役所→〇(但し代理人NG)
【必要書類】
・本人確認書類(役所窓口で交付を受ける場合)
・①からの委任状(②の場合)
・マイナンバーカード(コンビニ交付の場合)
ご存じの通り、世帯ごとにそこに属する人の住所、氏名、生年月日等が一人ひとり記載されている書類です(世帯=住所ではない点に注意!
例:世帯分離をした二世帯住宅やシェアハウスなどは同住所でも別々に世帯ごとの住民票が作られます)。
その住民票に記載されている本人の他、本人から委任を受けた代理人(委任状が必要。ひな型を管轄役所HPからダウンロード可能なことが多いです)が交付を受ける事ができます。
管轄の役所以外で交付を受ける方法として、マイナンバーカードを使用すれば全国のコンビニでも交付を受ける事ができるのはもうご存じの方も多いと思いますが、実はそれ以外にも管轄以外の役所窓口で住民票を交付してもらう事ができます(広域交付制度)。
たとえば「沖縄に単身赴任しているけれど住民票は北海道にある! マイナンバーカードもない!」といった場合には沖縄の市役所で北海道の住民票を交付してもらう事ができるという便利な制度ですが、一つ注意点として広域交付を利用するには本人が直接窓口へ行く必要があり、管轄の役所での交付と異なり代理人が請求できない点に注意です。
(私たちが遠方の住民票を依頼人の代わりに請求する際も、わざわざその管轄の役所まで赴く必要があります……)
戸籍謄本(除票)
【交付を受ける事ができる人】
① 戸籍に載っている本人
② ①の直系尊属(親、祖父母など)
③ ①の直系卑属(子、孫など)
④ ①②③から委任を受けた代理人
※②③以外の親族(きょうだい、おじおば、甥姪など)は原則的に請求できない点に注意
【管轄役所以外での交付】
コンビニ→〇 他管轄の役所→〇(但し代理人NG)
【必要書類】
・本人確認書類(役所窓口で交付を受ける場合)
・①②③からの委任状(④の場合)
・マイナンバーカード(コンビニ交付の場合)
こちらも住民票に並んで使用する機会が比較的多い書類かと思います。
戸籍に属している人の氏名、生年月日、父母の名前や出生地などが記載されています(実は戸籍謄本には現住所は載っていないのです。詳しくは「戸籍の附票」の項にて)。
戸籍に記載されている本人の他、その直系尊属と直系卑属……つまり親子や祖父母と孫などの関係性がある人(と、これらの人から委任を受けた代理人)が交付を受ける事ができます。
それ以外の親族は通常は交付を受ける事ができず、例えば兄や弟の戸籍を取得したい場合は委任状を書いてもらって代理人として交付を受ける必要があります。
(ただし、親の相続手続きに必要な場合など、正当な理由がある場合はそのこと証する書類を役所に提出する事で請求する事ができます)
こちらも住民票と同様にマイナンバーカードを使ってコンビニで取得できる他、他管轄で取得できる広域交付制度が令和6年3月1日から始まりました。代理人による交付請求ができない点も同様です。
戸籍の附票
【交付を受ける事ができる人】
① 戸籍に載っている本人
② ①の直系尊属(親、祖父母など)
③ ①の直系卑属(子、孫など)
④ ①②③から委任を受けた代理人
※②③以外の親族(きょうだい、おじおば、甥姪など)は請求できない点に注意
【管轄役所以外での交付】
コンビニ→〇 他管轄の役所→✕
【必要書類】
・本人確認書類(役所窓口で交付を受ける場合)
・①②③からの委任状(④の場合)
・マイナンバーカード(コンビニ交付の場合)
戸籍の附票と聞いてもピンと来ない方もいらっしゃるかもしれません。
これには戸籍謄本と一緒に役所に保管されている書類で、その戸籍に属している人の住所の履歴が記載されています。前述の通り、戸籍謄本には住所の記載がないため、戸籍に載っている人が実際にどこに住んでいるのか、住んでいたのかを調べる際はこの戸籍の附票が必要になります。
住所の移り変わりが載っているという点では住民票と似ていますが、住民票は一つ前の住所しか載っていないのに対して戸籍の附票はその戸籍に属している間の住所の異動の履歴全てが記載されるため、複数回転居した履歴も少ない通数で確認する事ができます。
(例えば、3回転居した人の住所の履歴を住民票(の除票)で調べる場合はそれぞれの住所地で合計3通の住民票を請求する必要がありますが、戸籍の附票であれば1通で事足りる可能性があります)
戸籍に付属する書類という事で、交付を受ける事ができる人の条件は戸籍謄本と同様です。
こちらもマイナンバーカードがあればコンビニで交付を受ける事ができますが、戸籍謄本と異なり広域交付制度は無いため本籍地管轄以外の役所で交付を受ける事はできません。
印鑑証明書
【交付を受ける事ができる人】
・誰でも
【管轄役所以外での交付】
コンビニ→〇(印鑑カード不要) 他管轄の役所→✕
【必要書類】
・印鑑登録証(印鑑カード)
・マイナンバーカード(コンビニ交付の場合)
住民票や戸籍謄本に比べると馴染みの薄い書類かもしれません(不動産の売買に関する登記では必ず登場するので私たちは毎日目にしていますが)。
こちらは実印の印影を証するための書類で、印鑑を登録した人の氏名、住所、生年月日、登録された印影が記載されています。
住民票、戸籍謄本や戸籍の附票は本人やその親族や代理人が取得できる書類だったのに対し、印鑑証明書は印鑑を登録した際にもらえる印鑑登録証(印鑑カード)を役所の窓口に持参すれば誰でも取得が可能です。
つまり、本人や本人から委任を受けた代理人である必要がないため、取得の際に本人確認書類や委任状も不要です(実際に私も依頼人から印鑑カードだけをお預かりして代わりに役所へ赴き、取得したことがあります)。
逆を言えば本人であっても交付を受ける際は印鑑登録証が必要なため、紛失した場合は実印を再登録し新しい印鑑登録証を発行してもらう必要があります。
印鑑証明書も住民票、戸籍謄本、戸籍の附票と同様にコンビニでマイナンバーカードを使用した交付が可能ですが、この場合印鑑登録証も不要です。また、広域交付制度は無いため管轄以外の役所で交付を受ける事はできません。
Ⅱ.法務局で交付を受ける事ができるもの
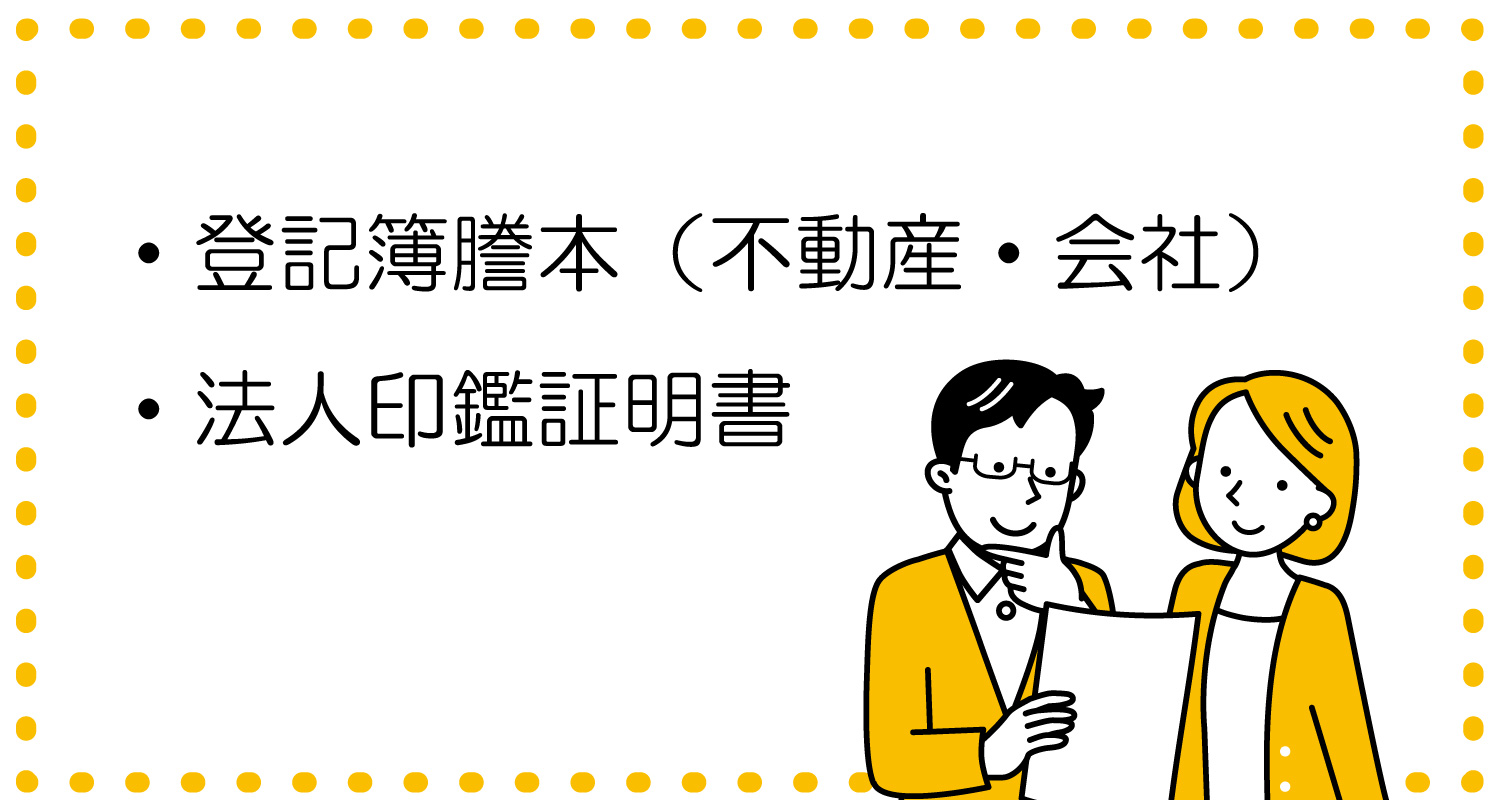
こちらはこれまでの書類と比べると取得する機会が1段落ちると思われます。
ただ、登記簿謄本(不動産)に関しては相続の際などに必要となる事が多い書類のため、手続きを自分で行う場合は一般の方でも取得する事があるかと思います。
登記簿謄本(不動産・会社)
【交付を受ける事ができる人】
誰でも
【必要書類】
・請求する不動産や会社の情報
→不動産
・所在(「住所」とは異なるので注意)
・地番(土地の場合)
・家屋番号(建物の場合)または不動産番号
→会社
・商号(名称)
・本店所在地(できれば市区町村まで)
・会社法人等番号
土地や建物、会社等の履歴事項が記載された証明書です。
数百円の手数料を支払えば誰でも(その不動産や会社と関係ない人でも)交付を受ける事ができます。
また、現在の登記簿はごく一部の例外を除いてほとんどが電子化済みのため管轄に関係なく取得する事ができ、例えば北海道にある不動産や会社の登記簿を沖縄の法務局で取得する事もできます。
ただし、実はわざわざ法務局に行って登記簿謄本を請求する必要はあまりありません。
「登記情報提供サービス」という非常に便利なサービスを利用する事でパソコンやスマートフォン等から登記簿のデータをダウンロードする事が出来てしまいます。
簡単に登録できて手数料はクレカ決済でOK!
しかも法務局で請求するよりも安いと良い事づくめ!
どうしても法務局の印が押された紙の謄本が必要な場合以外はこちらのご利用をお勧めします。
ちなみに、少しシーズンを過ぎてしまいましたが確定申告の住宅ローン控除の申請に必要な登記簿謄本は令和3年度分から「不動産番号」を申請書に記載する事で原本の省略が可能になったため、このためにわざわざ法務局で原本を請求する必要はありません。
法人印鑑証明書
【交付を受ける事ができる人】
誰でも
【必要書類】
・法人の印鑑カード
・代表者の生年月日
印鑑証明書の法人バージョンです。
取得する機会があるのは会社を経営している方ぐらいかもしれませんが一応簡単にご説明します。
役所で交付される個人の印鑑証明書と同様に、印鑑カードを持っていれば本人以外でも取得できますが、個人の物とは異なり交付の際に代表者の生年月日の入力が必要です(私はこの業界に入って間もない頃、代表の方の生年月日を確認し忘れて法務局に行ってしまい、その場で焦って事務所に電話をかけて確認してもらうという事がよくありました)。
Ⅲ.都税事務所(東京23区内) 市税事務所、役所(役場)の税務課などで交付を受ける事ができるもの
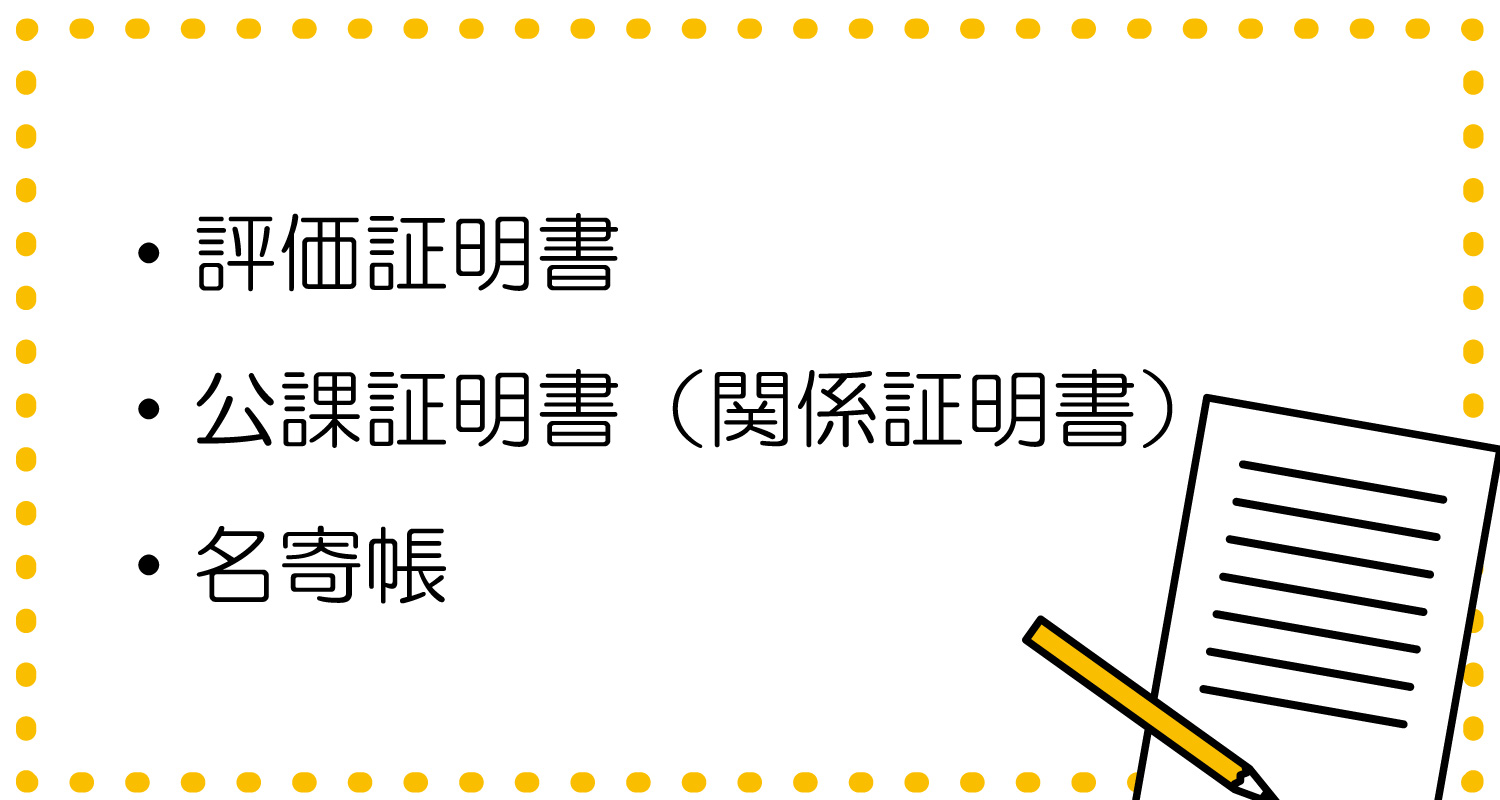
これらはいずれも不動産の評価額が記載されている書類です。
評価額は市区町村が算定した不動産の価格で、必ずしもこの価格で実際に売買されるというわけではありませんが、不動産に関する税金の算定基準になります。
使用するのは主に不動産を売却する時や不動産を相続する時でしょうか(通常の納税の際は、何もしなくても税務署から課税明細書が送られてくるため、わざわざ自分で評価額を確認する必要はありません)。
前者の場合は仲介業者が代わりに取得してくれるので自身での取得が必要になるのは相続の場合が多いです。
東京23区や一部の市区町村の場合は「都(市)税事務所」というあまり耳慣れない場所での交付となるため、いざ必要になった時にどう取得すれば良いか戸惑いやすいです(私も法務局に行った際など、都税事務所と間違えて法務局に来てしまった方をたまに目撃します)
評価証明書・公課証明書(関係証明書)
【交付を受ける事ができる人】
① 納税義務者(≒所有者)
② ①の相続人
③ 宅建業者
④ 賃借人
⑤ ①~④の代理人
【必要書類】
・本人確認書類
・戸籍謄本など、①との関係を証する書類(②の場合)
・媒介契約書(③の場合)
・賃貸借契約書や登記簿謄本など、①との関係を証する書類(④の場合)
・委任状+上記書類(⑤の場合)
不動産ごとの評価額が記載されている書類です(公課・関係証明の場合は固都税も)。
課税額も個人情報と考えられるため、基本的に納税義務者(その不動産の所有者)本人が取得できます。
本人が亡くなっている場合はその相続人(戸籍謄本などでそのことを証明する必要あり)が取得できます。
また、不動産売買の際にも必要となるため、不動産所有者と媒介契約を結んだ宅建業者も取得が可能です。
変わった所では賃借人(アパートを借りている人、土地を借りて自分の家を建てた人)も請求が可能です(家賃や地代に固定資産税が転嫁される場合がある事などから、不当に賃料を引き上げられていないかなどを確認できるようにするためです)。
なお、23区内の場合は管轄に関係なくどこの都税事務所でも請求が可能です(港区管轄の都税事務所で千代田区の評価証明書を請求など)。
名寄帳
【交付を受ける事ができる人】
① 納税義務者(≒所有者)
② ①の相続人
③ ①②の代理人
【必要書類】
・本人確認書類
・戸籍謄本など、①との関係を証する書類(②の場合)
・委任状+上記書類(③の場合)
評価証明書が不動産を指定して取得する書類であったのに対し、名寄帳は「人」ごとに所有する不動産の一覧が載っている書類です。
例えば故人がどんな不動産を所有していたかわからない場合、名寄帳を確認する事で所有していた不動産の一覧を手に入れる事ができます(ただし、管轄の都税事務所へ行かなければならないのである程度のあたりをつけて請求する必要はありますが……)。
評価証明書と同様に本人の他その相続人、本人や相続人から委任を受けた代理人が取得できます。
長くなってしまいましたが、私たちの業務でよく使用する公文書の取得方法をまとめてみました。
少しでも、これらの書類をご自身で取得される方のお役に立てれば幸いです。
ではまた次回の記事でお会いしましょう!

